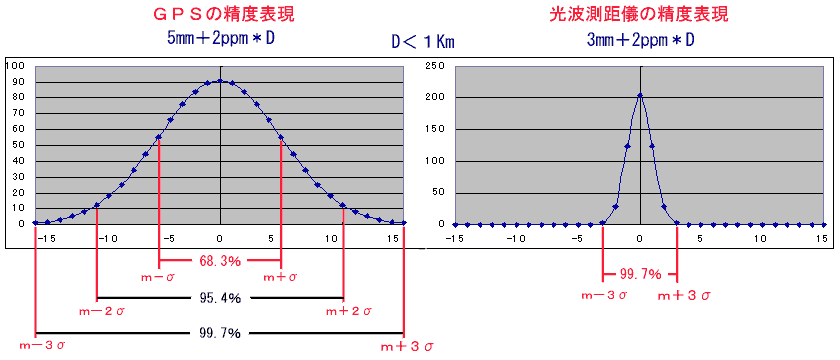|
GPSと光波測距儀との精度の表現の違いについて |
|
|
| GPSのカタログに記載されている測位精度と、トータルステーション(光波測距儀)のカタログに記載されている測距精度、ともに精度という表現がされいずれも測量器械であるため
、同じ基準で算出された数値であると認識してしまいます。(私だけなのかも?) GPSの場合、5mm+2ppm*Dとは全観測の68.3%が入る範囲1標準偏差( 1σ:シグマ)を示していて、光波測距儀では、3mm+2ppm*Dとは全観測の99.7%が入る範囲3標準偏差( 3σ)を示しています。本当は光波測距儀と同じ基準での表現にしてもらえた方が良いのですが。 解りやすく言うと、1km未満の距離を100回測ると、GPSでは68回(3分の2)は±5ミリ(計10ミリ)以内だけれど残り(3分の1)は範囲を超える可能性があり、光波測距儀では±3ミリ(計6ミリ)以内に全部入るが場合によっては1回だけ精度範囲を超える可能性があるということです。GPSを光波測距儀と同じ基準で表現すると、殆ど全て入る範囲は±15ミリ(計30ミリ )必要ということになります。 RTK−GPSの精度に関して殆どのメーカーのカタログには10mm+2ppm*Dと記載されています、このことは観測した場合その値は直径6センチの円内のどこかが求められたという事を意味するのではないでしょうか。 私の導入したメーカーカタログの場合だと、RTK−GPSの精度は固定時5mm+2ppm(rms)、移動時10mm+2ppm(rms)と1標準偏差であることが明記(?)されてい ますので観測成果が10ミリ以上になっても「RTK−GPSについて」の11段目のような説明が出来ます。もしこれが書かれてないなら、今までの測量器械は99.7%が入る範囲3標準偏差だったのですから 利用者は同様に解釈してしまうので、カタログ性能を満たしてないなんて文句を言われたらどう対応するのでしょうか。 もしかすると「マルチパスが多く発生してます」とか「衛星の切り替わ変わり目です」とか「衛星の配置が悪い」という再現性のない理由で誤魔化されてしまうかもしれません。 |
| 精度を悪くする要素としては、電離層の影響、衛星の数と配置、軌道歴、マルチパスなどが考えられています。ミスFIXなどというのもありました。「衛星の数と配置」は天空障害を観測計画ソフトに入力することによりDOPが計算出来るので、観測時間帯を選択すれば解決可能です。マルチパスは再現性がないのでやっかいです。逆にいうとマルチパスの影響がないと観測値は非常にまとまっています。 |