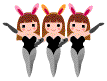
RTKでは土地家屋調査士の要求する精度・再現性を満足出来ないので電子基準点を与点とする2時間半スタティックで運用しています。

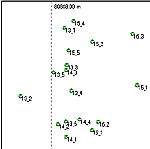
電子基準点を使ってサイカ523固定点を計測してみました

リアルタイムスタティックの検証
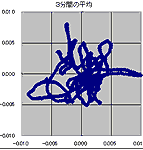
観測時間の長さと求まる平均値の変化について
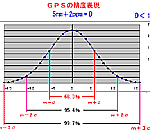
GPSと光波測距儀との精度の表現の違いについて
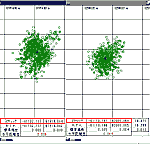
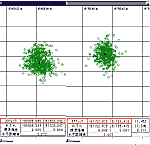
その3上段右 市道沿い 天空障害 良 アンテナ高3.1m
左 私道沿い 天空障害 並 アンテナ高3.6m
その3下段右 駐車場 天空障害 良 アンテナ高2.5m
左 グランド 天空障害 良 アンテナ高3.1m
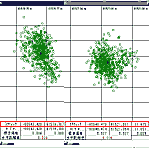
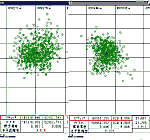
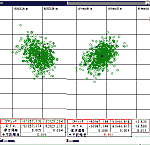
その1上段右 国道沿い 天空障害 良 アンテナ高3.3m
左 国道沿い 天空障害 良 アンテナ高3.5m
その1中段右 公園 天空障害 良 アンテナ高1.6m
左 公園 天空障害 良 アンテナ高3.1m
その1下段右 市道沿い 天空障害 良 アンテナ高3.0m
左 公園 天空障害 良 アンテナ高1.5m
その2上段右 国道沿い 天空障害 良 アンテナ高3.0m
左 市道沿い 天空障害 並 アンテナ高2.6m
その2中段右 グランド 天空障害 良 アンテナ高1.6m
左 私道沿い 天空障害 良 アンテナ高2.8m
その2下段右 公園 天空障害 並 アンテナ高3.6m
左 私道沿い 天空障害 並 アンテナ高3.0m
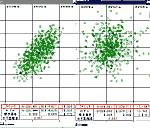
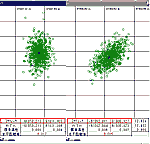
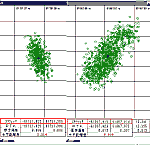
6月末に観測した現場です、境界はTSで測量して基準点トラバーは可能な限りGPSにより観測しました。1点あたり1秒観測を20分間(いつもは15分間ですが余裕をみて)1200秒の平均値を観測値とします。梅雨までにTSによる事前測量を終了したいため風が強かったのですが、27点(天空障害 良16点、並9点、悪2点)を無線モデムRTK−GPSで観測する予定で作業を開始しました。天空障害とマルチパスの影響を避けるためアンテナを2m〜3m上げて観測したのですが、画像のとおり風によりアンテナが微振動したみたいで観測値が長い楕円になってしまいました。それと森の中の点では30cmの幹が何本も重なっているため捕捉している衛星数が頻繁に3個になって日中の時間帯では殆ど連続観測が出来ない状態でした。20分間の連続観測の標準偏差も思わしくないので18点観測した時点でスタティックに切り替えることにし、急遽メーカーから4台を拝借して全点を短縮スタティックで観測しました。
RTKとスタティックの結果を比較してみました、全点というわけにはいきませんが掲載してみます。解説は「その2」でさせて下さい。
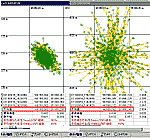
無線モデムはまだ戻ってこないのですが、観測値の異常なバラけが気になるので代替機の無線モデムでなくケーブル直結でテストしてみました。右が16日に観測したもの、左が今日18日の観測したもの、今日の観測では80%が5mm以内に入っていて全く正常な観測値になっています。東京でも同様のテストをしてもらいましたが、さすがに高さ124mのビルの屋上だと全て5mm以内に収まっていました。ということは16日の尋常でない観測値は固定局のデータが移動局に正しく伝わらなかったことが原因で、軍事行動のためGPS衛星が調整されていたわけでないことが解りました。
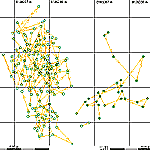
ナッナンダー!「この器械は5mm+2ppmなんだから32mなら観測値は5mm以内じゃないのか!」とメーカーに怒鳴り込みました。
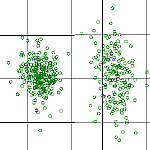
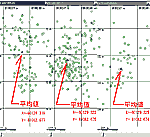
B=35 27 15.8048 L=133 03 36.6966 X=-60158.263 Y=81098.239 標高=2.32 (3系)
とすることにしました。松江市以外の区域を測量する場合は、ライカ独自のRTKによるローカル座標決定機能を使うとXYについては1cm程度の差で求まるので当面は上を固定局座標として使うことにして実用に入りましたが!
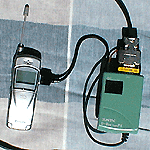
PHSは携帯電話と異なり通常は一般電話とのデータ通信は困難です。例外なのがDDIポケットで、アルファデータ対応のモデムを使うと一般電話や携帯電話とデータ通信が可能です。 画像の左は月額基本料980円の安心だフォン、右がサン電子の対応モデムD-BOX typeP1です。ACアダプタを使う据置型ですが低消費電力なのでACアダプタの線を切って乾電池ボックスに接続し単3型ニッケル水素充電池で動作させています。これだと携帯電話に比べて20円ですみます。

2000年12月20日 接続テストを行ったところOK、これで移動局から携帯電話モデムと一般電話モデムを経由して固定局が接続可能となり無線モデムを使用したのと同様に(電話なので距離の制限なし)RTK-GPSを使用した測量が可能となりました。
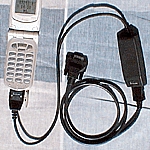
2000年11月29日 本体と携帯電話モデムを接続する専用ケーブルが到着
2000年12月3日 移動局の携帯電話から固定局の一般電話を呼び出すテストを行ったが、固定局が全く応答せず。やむなく本体とモデムとケーブルを返送。Leicaでの調査ではケーブルの結線ミスと本体内のソフトが電話モデムのATコマンドに対応してなかったのが原因とのことなので、ソフトの入れ替えとケーブルの作り直しを早急に対処してもらう様に依頼しました。
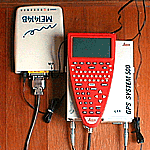
この画像は現在の姿ですが、当初は電話用モデムは接続してなくて送信用無線モデムが接続されていました。でも特定小電力の無線モデムは全く距離が飛ばないため、ネットの無線機のサイトでもっと飛ぶ機種を検索するが9600bps以上の伝送速度が可能なのは特定小電力タイプしかみつかりませんでした。違法に高出力するブースターを接続しようかと考えましたが、電監に機器を没収されるのが怖くて断念しました。デモの際に無線の到達距離に不安があったので携帯電話接続の構成も可能なように発注していたので、固定局を一般電話で移動局を携帯電話にして運用することに決定し納入を催促しました。

固定局は全衛星を捕捉するために天空が開けていることが重要ですが、忘れてならないのが設置した固定局を他人にかってに触られないことも必要です。そこで当事務所南側の内庭に特大三脚を立てることにしました。アンテナ高を3.365mにすると天空障害はありません。固定局本体は事務所建物の内におきアンテナとは10mのケーブルで接続しています。普段は三脚と脚立は立てっぱなしで測量に出かける前に整準台から上を取り付けます。

移動局側の受信専用無線ムデムは本体と一体になっているのでアンテナは直付かケーブル接続で1m上げる程度、そこで問題発生!市街地にある事務所付近では無線が200m程度しか飛ばないことが判明、事務所の屋根の上に固定局送信モデムを設置して半径2kmの市内を無線モデム使用で測量する計画が実行不能となる。

2000年9月8日 銀行からの融資決定が降りたので後処理ソフトなしの構成で発注
2000年10月25日
待ちに待ったライカのRTK-GPS530が到着、ただし携帯電話モデムと専用ケーブルは少し遅れるとのことでした。右が固定局本体、左が10mのケーブルで繋がった送信専用の無線モデム、防水ケースに入っているので写真とは別のポールで7mの高さに設置。

1999年に法17条地図作製の際に設置した基準点においてライカ、トプコン、ジオジメータのデモを見せてもらう。100から600mの範囲を観測するがマンションがあると100m以内でも無線モデムが届かない器械があった。法17条作製の際に苦労して測量した4級基準点を10秒程度の観測ですむことに感動して導入しようと考えるようになる。ただし無線モデムの到達距離に不安があるため携帯電話も利用可能な機種を検討する。