観測時間の長さと求まる平均値の変化について
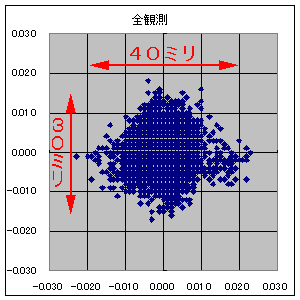
私の観測は、座標値の制限(バラつきの制限範囲を指定する機能です)をかけていません。というのは、 仮に20ミリと指定した時どの点の座標を基準にしているのかが不明なので観測されたオリジナルの平均を利用したいからです。
下は右の観測値から10秒間、3分間、15分間の平均を取ってものです。全観測が6720個あるので10秒間平均は6710個、3分間平均は6540個、15分間平均は5820個計算出来ます。なぜこんな計算をしたかといいますと、もしこの112分間のあいだに全く同条件で10秒間、3分間、15分間のいずれかの観測をして平均値を求めた場合、下の相当する図のプロットと対応していることになるからです。
プロット図の縮尺が異なるのでご注意!
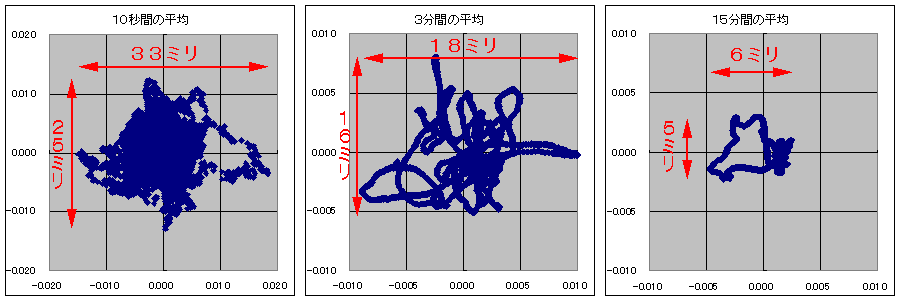
10秒間平均を取った場合X幅25ミリ Y幅33ミリの範囲になり、1秒観測と同様に躊躇します。
3分間平均を取った場合X幅16ミリ Y幅18ミリの範囲になり、観測する点間距離が短いと躊躇してしまいます。
15分間平均を取った場合X幅5ミリ Y幅6ミリの範囲になり、97分間のうち何時からでも15分間観測すればピンポール径より少ない誤差で測点の座標値が求まることになります。
導入から1年になろうとしていますが、何十回もの観測から満足する精度を求めるには15分間以上の連続観測による平均が必要だという結論になりました。 連続観測中に観測データの標準偏差と平均が表示可能ならば、データのバラつきが解るので観測時間の長短が調整出来て便利なのですが。